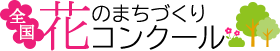第31回(2025年)全国花のまちづくり牧之原大会

テーマ 『花と共に 人と共に 牧之原市』
5月31日・6月1日、静岡県牧之原市で「全国花のまちづくり牧之原大会」が開催されました。花のまちづくりを全国各地に普及定着させるために毎年開かれるこの大会は、今回で31回を数えます。誌面では、地域の活動事例、先進地事例発表、現地見学会の様子をご紹介します。なお式典では、園芸研究家の矢澤 秀成氏と園芸デザイナーの三上 真史氏によるスペシャルトークショーも行われました。
事例発表*トークディスカッション「花づくり・人づくりで地域を元気に」
トークディスカッションでは、牧之原市内で花と人づくりを通して地域を元気にする活動を続ける団体・学校が登壇。各団体の活動をご紹介します。
牧之原市花の会
2006年、前年の牧之原市誕生を機に「さがら花の会」と「榛原町花の会」が合併して発足。今年で20周年を迎えました。花が大好きで「花で地域を良くしたい」という思いは皆共通です。「花いっぱいの花壇づくり」も継続しつつ、最近は花や緑の良さを皆で楽しむ活動を心がけています。
10年前からは花育活動も始め、夏休みなどに子どもたちと一緒に活動したり、矢澤 秀成先生の講習会でペチュニアを交配させ、世界に一つの花を育成する取り組みもしています。活動を無理なく持続させるために、まず自分の身体と家庭を一番に考え、困った時には誰かに相談するなど、頑張りすぎないことを心がけています。「花の会の花壇は皆さんのお庭代わり」という思いで活動を続けていきます。
萩間小学校

地域と共に活動に取り組む萩間小学校
50年以上前から花壇活動が行われ、「花といえば萩間小学校」というイメージが定着しています。花いっぱい委員会の児童たちを中心に活動し、花壇のデザインは毎年全校児童から募集。昨年は約140名の児童数で100点ほどの応募があり、その中から全校児童による投票で決定しています。
台風時には花苗を校舎内に避難させる作業を委員会以外の生徒が手伝うなど花への愛着が育まれており、夏休みなどには卒業生が花の世話をしに来てくれます。
教育現場では生徒も教員も毎年入れ替わるため、できる範囲で活動を継続させていくことが大切です。植える花は宿根草や多年草を取り入れ、地域の方々の力を借りて活動しています。コンクールでの受賞を目的とするのではなく、子どもたちが種を蒔き、芽が出て花が咲いた時の喜び、感動する心を育てるという本来の目的に立ち返り、花づくりを続けていきたいと思います
川崎地区絆づくり

川崎地区絆づくり
(写真提供:牧之原市)
地域の課題解決に取り組む牧之原市の「地域の絆づくり事業」の一つで、「学校、家庭、地域に居場所を」をコンセ プトに活動しています。児童館に隣接する市有地の空き地を7年がかりで整備した「せせらぎガーデン」は、地域の方々との対話から始まりました。通りすがりの小学生や親子が花壇づくりに参加してくれるなど多世代交流が出来る場所となり、緑の環境プラン大賞でコミュニティ大賞を受賞しました。最近新設された図書館の庭に整備した花壇では、本に携わる方にも最初から対話に参加してもらい、多様な人々が楽しめるデザインを心がけました。
当番制にせず、できる人ができる時に、点が線や面になればと活動を続けてきた結果、他の地域の団体との繋がりもできました。いずれは通学路をフラワーロードにしたいと考えています。
勝間田区絆づくり事業

勝間田区絆づくり事業の皆さん
(写真提供:牧之原市)
芝で緑化している「ゆうゆうらんど」を中心に皆で楽しめる場所づくりを行っています。芝生と花を植え、皆の笑顔あふれる広場ができました。
市長も参加し、勝間田区の住民総出で活動しています。昔から花壇づくりを 行ってきた会と、「ハワイのようにハイ ビスカスを植えたい」という若い団体が一緒に活動し、イベントも行っています。高齢で活動が難しくなった時に「のれん分け」のように若い方たちに世代交代を進めるには、親が楽しそうに花植えや地域づくりに取り組む姿を見せることで、子どもたちも「やってみようかな」と自然に思える循環をつくることが必要だと思います。花のある景色は人がつくっていることを念頭に、花を通じて人が幸せを感じられる景色をつくっていきたいです。
全国先進事例発表
特定非営利活動法人田原菜の花エコネットワーク(愛知県田原市)
「菜の花をキーワードに資源循環型社会を目指す」

菜の花をキーワードに多彩に活動する
(写真提供:田原菜の花エコネットワーク)
田原市は花卉や野菜を中心に農業が盛んです。団体は2006年に設立。耕作放棄地問題解決のため、遊休
農地での菜の花やヒマワリの栽培を通じて景観美化や農地の健全化を目的に活動を始めました。田原市の主要施策の一つとして菜の花をキーワードに資源循環型社会の形成を目指しています。活動の5本柱は、①資源循環:菜種の油かすは肥料に、廃油は燃料再生利用。②遊休農地解消。③景観美化。④菜種搾油・販売。⑤普及啓発:保育園や学校での「種まき体験」「菜種刈り・搾油体験」「菜の花交流」「市民向け環境学習イベントの開催、出展」などです。
菜の花を活用した美しい農村景観は「日本風景街道」に登録され、菜の花エコサポーターや地元企業とも協力しながら花のまちづくりを行っています。第34回全国花のまちづくりコンクールでは大賞の農林水産大臣賞を頂き、田原市全体が菜の花で繋がるまちづくりをしていきたいと思います。
現地見学会
式典は約470人、交流会は100人、翌日の現地見学会は50人が参加しました。見学会は2コースに分かれて、市民主体で築かれた花のまちづくりの活動拠点地「女神花壇」「せせらぎガーデン」「いろ葉の庭」「萩間小学校」などを見学したほか、多彩で高い品質を誇る花卉圃場「ガーベラハウス」「トルコギキョウハウス」、花の名所「秋葉公園」「大鐘家」などを巡り、充実の見学会となりました。

川崎地区絆づくりによるせせらぎガーデン
萩間
小学校にて
花卉圃場トルコギキョウハウスの生産者・広畑氏

花卉圃場ガーベラハウスにて生産者・加藤氏
花庄屋と呼ばれる大鐘家
花鉢のおもてなし
大盛況のおもてなしマルシェ
式典会場内外では、地域の高校生や花卉生産者、ボランティア団体など、56出展者による「おもてなしマルシェ〜花と笑顔に会いに行こう〜」が開催され、約1,000人が訪れました。花卉生産が盛んな牧之原市ならではの鮮度の高い花々や特産品の販売、花関係のワークショップ、展示などで会場が華やかに彩られました。
次回の全国花のまちづくり地方大会は、北海道恵庭市で2026年6月27日、28日に開催を予定しています。

朝から賑わうおもてなしマルシェ
センスあふれる花苗販売ブース
地域で生産されたハイナンガーベラや
トルコギキョウ、カスミ草、ユリなど
が会場内外を彩った

菜の花をキーワードに多彩に活動する
(写真提供:田原菜の花エコネットワーク)
田原市は花卉や野菜を中心に農業が盛んです。団体は2006年に設立。耕作放棄地問題解決のため、遊休 農地での菜の花やヒマワリの栽培を通じて景観美化や農地の健全化を目的に活動を始めました。田原市の主要施策の一つとして菜の花をキーワードに資源循環型社会の形成を目指しています。活動の5本柱は、①資源循環:菜種の油かすは肥料に、廃油は燃料再生利用。②遊休農地解消。③景観美化。④菜種搾油・販売。⑤普及啓発:保育園や学校での「種まき体験」「菜種刈り・搾油体験」「菜の花交流」「市民向け環境学習イベントの開催、出展」などです。
菜の花を活用した美しい農村景観は「日本風景街道」に登録され、菜の花エコサポーターや地元企業とも協力しながら花のまちづくりを行っています。第34回全国花のまちづくりコンクールでは大賞の農林水産大臣賞を頂き、田原市全体が菜の花で繋がるまちづくりをしていきたいと思います。
式典は約470人、交流会は100人、翌日の現地見学会は50人が参加しました。見学会は2コースに分かれて、市民主体で築かれた花のまちづくりの活動拠点地「女神花壇」「せせらぎガーデン」「いろ葉の庭」「萩間小学校」などを見学したほか、多彩で高い品質を誇る花卉圃場「ガーベラハウス」「トルコギキョウハウス」、花の名所「秋葉公園」「大鐘家」などを巡り、充実の見学会となりました。

川崎地区絆づくりによるせせらぎガーデン
萩間 小学校にて
花卉圃場トルコギキョウハウスの生産者・広畑氏

花卉圃場ガーベラハウスにて生産者・加藤氏
花庄屋と呼ばれる大鐘家
花鉢のおもてなし
式典会場内外では、地域の高校生や花卉生産者、ボランティア団体など、56出展者による「おもてなしマルシェ〜花と笑顔に会いに行こう〜」が開催され、約1,000人が訪れました。花卉生産が盛んな牧之原市ならではの鮮度の高い花々や特産品の販売、花関係のワークショップ、展示などで会場が華やかに彩られました。
次回の全国花のまちづくり地方大会は、北海道恵庭市で2026年6月27日、28日に開催を予定しています。

朝から賑わうおもてなしマルシェ
センスあふれる花苗販売ブース
地域で生産されたハイナンガーベラや
トルコギキョウ、カスミ草、ユリなど
が会場内外を彩った